初回限定無料
都会のサウンドトラックとして親しまれているシティポップとは?
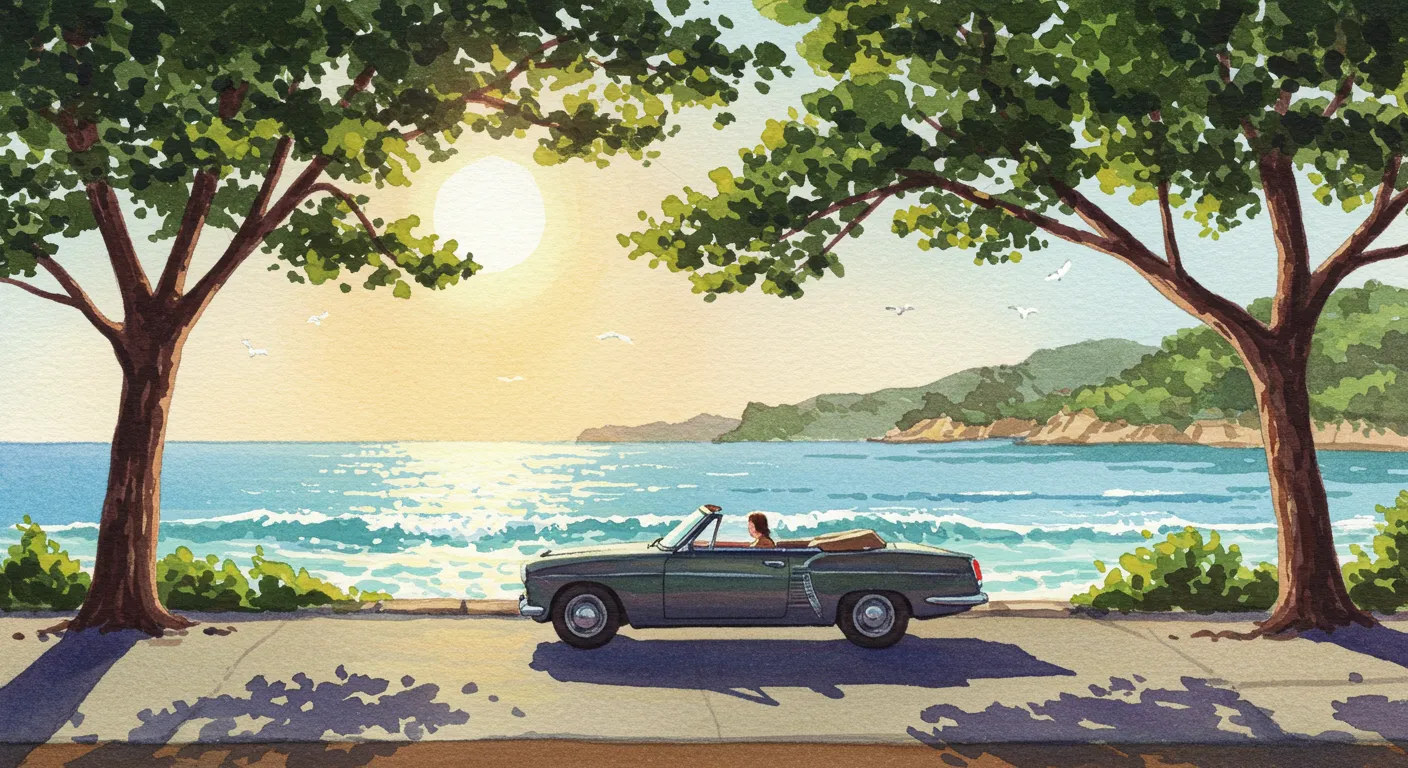
はじめまして。音楽とカルチャーの世界を日々探求しているamaneです。突然ですが、皆さんは「シティポップ」という言葉に、どんなイメージを抱きますか? 都会の夜景、夏のドライブ、洗練されたカフェ……。そんなキーワードが頭に浮かぶかもしれません。かつて1970年代から80年代にかけて日本で流行したこの音楽ジャンルが、今、時を超えて世界中のリスナーを魅了しています。特に驚くべきは、リアルタイムでその時代を経験していない海外の若者たちが、日本の古い楽曲に熱狂しているという事実です。
なぜ、国境や世代を超えて、シティポップはここまで愛されるようになったのでしょうか? それは単なる音楽の流行り廃りを超えた、ある種の「文化現象」と捉えることができます。この記事では、シティポップがどのようにして生まれ、なぜ一度は衰退し、そして今再び光を浴びているのかを、音楽的な側面だけでなく、社会的・文化的背景から多角的に掘り下げていきます。
 amane
amane歴史やアーティストの羅列ではなく、この音楽が持つ空気感と、時代が描いた夢の正体に迫る旅に、一緒に出かけてみましょう!

amane
Lo-Fiやシティポップ、ジャズなどを好む愛知県出身のWebライター。自身でもトラック制作を行なっており、趣味で会社員をしながらDJとしても活動中。
・シティポップの魅力や歴史を詳しく知りたい人
・昭和、平成のレトロで都会的な音楽に興味がある人
・日常におしゃれで洗練された音楽を取り入れたい人

第1章:シティポップとは何か?
曖昧なジャンル分け
シティポップという言葉は、実は「こうでなければならない」という厳密な定義が存在しません 。音楽評論家の金澤寿和さんも、このジャンルには「ハッキリした定義や境界はない」と指摘しています。その出自を辿ると、シティポップはそもそも音楽家たちが意図して作ったジャンル名ではなく、1970年代後半から音楽誌やレコード会社が、南佳孝や山下達郎、大滝詠一といった都会的で洗練された音楽を表現するために用いた「宣伝文句」や「和製英語」でした 。
 amane
amaneシティポップの代表的なシンガーの1人、大瀧詠一の代表曲『君は天然色』は、爽やかなメロディーや透き通るような歌声が魅力。この曲から同ジャンルに目覚めた人もおられるのではないでしょうか。
この言葉がもたらした柔軟性が、シティポップをより大きな概念へと押し上げました。特定のコード進行やリズム、楽器構成で定義されるのではなく、「洋楽志向が強くて都会的洗練度の高い和製ポップス」という「空気感」こそがその本質だったのです 。
ロック、ポップス、ソウル、ジャズ、フュージョン、ボサノヴァなど、幅広い洋楽のエッセンスを貪欲に取り入れながら 、日本語のメロディと融合させた独自のサウンドは、日本独自の都会的なポップミュージックとして発展しました 。
この柔軟性があったからこそ、様々なアーティストが「シティポップ」という大きな傘の下に収まり、今日では「ネオ・シティポップ」として新たな世代へと継承されるに至っているのでしょう 。
洋楽志向が生んだ都会的サウンド
シティポップのサウンドを形作る要素は多岐にわたります。まず、楽器の面ではシンセサイザーやエレクトリックピアノなどのデジタル音楽機器が多用され、サウンドに都会的で洗練された雰囲気を加えています 。リズムは、ファンクやソウルミュージックに影響を受けた16ビートが基調とされ、特にギターのパーカッシブなカッティング奏法や、指弾きベースのスラップを併用したグルーヴが特徴的です 。
コード進行においても、メジャーセブンスコードや、ナインス(9th)、イレブンス(11th)、サーティーンス(13th)といったテンションノートが頻繁に用いられ、ジャズやAOR(Adult-Oriented Rock)のような豊かで洗練された響きを生み出しています 。
このような複雑でありながらも耳馴染みの良い音楽性は、当時の日本の音楽シーンにおいて、革新的でありながらも大衆に受け入れられる普遍的な魅力を生み出しました。
街、バカンス、そして物語
大橋純子さんのテレフォン・ナンバーは、当時の日本のカルチャーを歌詞に取り入れながらも、都会的なエッセンスを十分に含んだ名曲。
歌詞はシティポップのもう一つの重要な要素です。テーマの中心は「街や都会、あるいは都市生活者がバカンスで訪れるようなプチ・リゾート」に設定されており、聴く人を非日常の、少しオシャレな世界へと誘います 。山下達郎氏が、個人的な内面を吐露する「四畳半フォーク」の世界観を毛嫌いしたという話が示すように 、シティポップの歌詞はメッセージ性よりも「語感やメロディとの親和性」を優先した抽象的な描写が特徴です。
また、シティポップの楽曲はCMソングとして数多く起用されました 。これは、楽曲自体が広告のキャッチコピーのように、聴く人々に特定のライフスタイルや雰囲気を強く想起させる美学を持っていたからです。音楽と消費文化が密接に結びつき、楽曲が持つ物語性が、リスナーの憧れを掻き立てたのでしょう。
 amane
amaneシティポップの最大の魅力は、その定義の曖昧さにあると思っています。明確な枠組みがないからこそ、リスナーは一人ひとりの心の中に、自分だけのシティポップを形作ることができます。ある人にとっては夏のドライブに欠かせないグルーヴであり、またある人にとっては雨の日の夜に聴く都会のジャズであり、そして別の誰かにとっては、遠い昔に憧れた「大人」のライフスタイルを追体験するサウンドトラックです。
第2章:時代が育んだ音楽
シティポップの歴史は、日本の社会や文化の変遷と深く結びついています。その流れを理解するために、まずは主要な出来事を年表で振り返ってみましょう。
| 年代 | 主な出来事・背景 | 象徴的なアーティスト・作品 | ||
| 1970年代前半 | 高度経済成長と都市化の進展 | はっぴいえんど『風街ろまん』(1971) | シュガー・ベイブ結成 | |
| 1975年 | 大滝詠一、ナイアガラ・レーベル設立 | シュガー・ベイブ『SONGS』 | ||
| 1970年代後半 | 音楽誌で「シティ・ポップス」が使われ始める | 荒井由実『COBALT HOUR』(1975) | 山下達郎『CIRCUS TOWN』(1976) | |
| 1980年代前半 | バブル経済の到来 ウォークマン、カーステレオ普及 | 寺尾聰『Reflections』(1981) | 大滝詠一『A LONG VACATION』(1981) | 山下達郎『FOR YOU』(1982) |
| 1984年 | 竹内まりや『VARIETY』 | (「Plastic Love」収録) | ||
| 1990年代 | バブル崩壊 「J-POP」ブームの到来 | シティポップの停滞と衰退 | ||
| 2010年代以降 | YouTube、ストリーミングサービス普及 ヴェイパーウェイヴ、フューチャーファンクの台頭 | 松原みき「真夜中のドア〜stay with me」 | 竹内まりや「Plastic Love」の世界的再評価 |
黎明期(1970年代)
シティポップが生まれた背景には、1970年代の日本の高度経済成長と都市化の進展があります 。新しいカルチャーやライフスタイルが都市部で発展するにつれ、若者たちはより自由で洗練された生活を求め、それを彩る音楽が必要とされました。
この流れの中で、はっぴいえんどのような先駆者たちが、日本語の歌詞で洋楽的なサウンドを表現する試みを始めました 。彼らの活動は、のちに山下達郎や大貫妙子が所属したバンド、シュガー・ベイブへと受け継がれ、1975年にリリースされた唯一のアルバム『SONGS』は、日本の音楽史に残る名盤としてシティポップの基礎を築きました 。
また、大滝詠一が敬愛するフィル・スペクターのフィレス・レーベルを模範として設立した「ナイアガラ・レーベル」は、スタジオでの緻密なレコーディングとプロデュースを重視する「プロダクションの美学」を確立しました 。これは、単に楽曲を作るだけでなく、完璧なサウンドと世界観を創り上げるという、後のシティポップに不可欠な精神を生み出しました。
黄金期(1980年代)
1980年代に入ると、シティポップは日本の音楽シーンで一大ブームを迎え、その黄金時代を築き上げます 。この時期は、ちょうど日本がバブル経済へと突入していく時代と重なります 。豊かさを享受するライフスタイルが広がり、「ウォークマン」や「カーステレオ」といった新しいメディアが登場したことで、音楽は「自宅で聴くもの」から、よりパーソナルな空間や都市空間へと持ち出されました 。
この時代に、寺尾聰のアルバム『Reflections』が160万枚以上、大滝詠一の『A LONG VACATION』が100万枚を超えるセールスを記録するなど、シティポップは社会現象となりました 。これらの音楽は、自家用車を所有し、都市のナイトライフやバカンスを楽しむ、経済的に余裕のある大人のリスナーをメインターゲットにしていました 。彼らは、政治的なメッセージや社会へのフラストレーションが薄い、ノンポリ的なシティポップの姿勢に共感しました。
シティポップは、単にバブル期に流行した音楽ではありませんでした。それは、当時の日本が追い求めた「豊かさ」や「憧れ」、そしてどこか現実離れした「ユートピア」のイメージを音楽的に表現した「文化的な産物」だったのです。バブル崩壊とともにシティポップのブームが終焉したことは、この音楽と時代の空気がどれほど密接に結びついていたかを物語っています 。
J-POPへの移行(1990年代)
1990年代に入ると、バブル崩壊後の社会に停滞感が漂い始めます。また、バンドブームの到来や「J-POP」という広範なジャンルの台頭により、シティポップという概念は次第に存在感を薄めていきました 。多くの楽曲が「J-POP」のカテゴリーの中に埋もれていき、一時代のブームは終わりを告げたのです。
第3章:シティポップを彩る要素
シティポップを構成する音楽的要素
シティポップの「洗練された」サウンドは、特定のジャンルではなく、様々な音楽的要素の巧みな融合によって生み出されました。以下に、その主な構成要素をまとめます。
| 構成要素 | 特徴 | 関連ジャンル・備考 |
| 影響を受けたジャンル | ロック、ポップス、ソウル、ジャズ、フュージョン、ボサノヴァ、AORなど、多岐にわたる洋楽 。 | 和製ポップスと洋楽のミクスチャー |
| 主な使用楽器 | シンセサイザー、エレクトリックピアノ、ブラスセクション、クリーントーンのギター、指弾きベース | 最新の録音技術や機材を積極的に導入 |
| リズムとグルーヴ | 16ビート(特に裏拍へのアクセント)、パーカッシブなギターカッティング、スラップを併用したベースライン | ドライブや夜の街に合う雰囲気を演出 |
| コード進行 | メジャーセブンス系コード、テンションノート(9th, 11th, 13th)の多用 | ジャズやAORに由来する、複雑で豊かな響き |
永井博、鈴木英人らが描いた「憧れの風景」
シティポップの魅力は、聴覚だけにとどまりません。音楽を聴く前から、私たちはそのアートワークに心を奪われました 。アルバムジャケットに描かれたイラストは、この音楽が目指す世界観を視覚的に表現し、聴く人々の想像力を掻き立てる重要な役割を担いました。
この視覚的美学を確立したのが、イラストレーターの永井博と鈴木英人です。永井博氏の作品は、シンプルな構図と、プールサイドや建物、道路の絶妙なパースが特徴です 。特に、目線を低く設定して大胆に描かれた空のグラデーションには、どこか哀愁が漂い、異国情緒を象徴するパームツリーがすらりと伸びる風景は、このジャンルの「開放的でありながら、どこか寂しい」という独特の雰囲気を完璧に捉えています 。
大滝詠一の名盤『A LONG VACATION』のジャケットが、もともと永井博氏のイラストブックから生まれたという逸話は、音楽とアートワークがどれほど深く結びついていたかを物語っています 。
 amane
amane当時の私は、レコードやカセットテープを手に取った瞬間から、その音楽の旅が始まっていました。永井博さんや鈴木英人さんの描く、抜けるような青空とパームツリー、そして夕暮れのプールサイドのイラストは、まだ見ぬ憧れの場所や、まだ経験したことのない夏の物語を想像させてくれました。音楽を聴く前から、ジャケットがすでに一つの「物語」を語りかけていたのです。シティポップは、視覚と聴覚が一体となって、私たちの心に「憧れ」の風景を描き出す、非常にユニークな文化体験でした。
ウォークマン、カーステレオ、FMラジオ
シティポップは、単なる音楽ジャンルではなく、当時のライフスタイルそのものと深く結びついていました。車社会が広がり、「カーステレオ」が普及したことで、音楽は街や高速道路といった都市空間の「サウンドトラック」となり、「ドライブに合う音楽」というイメージが定着しました 。
また、レコードやCDを買うお金がなくても、友人同士で音楽を共有できる「カセットテープ」は、当時の若者にとって重要なコミュニケーションツールでした 。お気に入りの曲を集めて手作りのミックステープを作り、それをプレゼントする文化は、シティポップの伝播に一役買いました。
さらに、当時の音楽雑誌『FM STATION』は、鈴木英人氏のイラストを表紙に起用し、音楽とビジュアルを融合させたライフスタイルを提案していました 。深夜のFMラジオから流れる洋楽ライクなサウンドと、都会的なイラストが一体となり、当時の若者たちの憧れを形成したのでしょう。
第4章:なぜ世界から人気を集めているのか?
シティポップが現代で再評価された最大の要因は、インターネットとストリーミングサービスの普及です 。特に、YouTubeの「アルゴリズム」が果たした役割は決定的でした。松原みき「真夜中のドア〜Stay With Me」や竹内まりや「Plastic Love」などの楽曲が、海外のリスナーに次々と推薦され、再生回数が爆発的に増加しました 。
この現象は、あたかも現代版の「口コミ」のように、特定のファン層から新たな層へと広がり、シティポップは日本の「懐メロ」から、世界中で聴かれる音楽へと変貌を遂げました。
ヴェイパーウェイヴとフューチャーファンクの源流
シティポップの再評価を語る上で欠かせないのが、インターネット発の音楽ジャンル「ヴェイパーウェイヴ」と、その派生である「フューチャーファンク」です 。フューチャーファンクは、「シティポップのサンプリングに、ダフト・パンク風のアレンジ」を加えることを特徴としており、このジャンルのクリエイターたちが日本の古い音源を積極的に発掘・利用しました 。
この結果、シティポップは世界中のクリエイターが新しい作品を生み出すための「音の素材」として再定義されました。この動きが、新しいリスナー層をシティポップの原曲へと導き、ブームを加速させたのです。
YouTube再生回数推移
シティポップの世界的な再評価は、YouTubeでの特定の楽曲の再生回数に顕著に表れています。
- 2010年代前半:
- 再生回数は緩やかに推移。
- 2010年代半ば:
- ヴェイパーウェイヴやフューチャーファンクの台頭により、これらの楽曲がサンプリングされる。
- 2017年〜2018年頃:
- YouTubeアルゴリズムが、ユーザーの視聴履歴に基づいて「Plastic Love」や「真夜中のドア」を次々と推薦し始める。
- 2010年代後半〜現在:
- 両楽曲の再生回数が爆発的に増加。動画のコメント欄は多言語で溢れかえり、グローバルな現象へと発展する。
このグラフが示すように、テクノロジーが、時間と国境という障壁をいかに簡単に取り払うかを見て取ることができます。
第5章:時代を超えて輝く名曲・名盤ガイド
ここからは、シティポップの旅を始める上で、絶対に外せない金字塔と呼べる作品群を紹介します。
必聴!シティポップ名盤リスト
| アーティスト | アルバム名 | リリース年 | 代表曲 |
| 大滝詠一 | 『A LONG VACATION』 | 1981年 | 「君は天然色」「雨のウェンズデイ」 |
| 山下達郎 | 『FOR YOU』 | 1982年 | 「SPARKLE」「LOVELAND, ISLAND」 |
| 竹内まりや | 『VARIETY』 | 1984年 | 「プラスティック・ラブ」 |
| 寺尾聰 | 『Reflections』 | 1981年 | 「ルビーの指環」「SHADOW CITY」 |
| 松原みき | 『POCKET PARK』 | 1980年 | 「真夜中のドア〜stay with me」 |
| 荒井由実 | 『COBALT HOUR』 | 1975年 | 「ルージュの伝言」「卒業写真」 |

代表的アーティストとその功績
シティポップというジャンルは、個々の偉大なアーティストたちの功績によって築かれました。
大滝詠一:日本のポップミュージック史における伝説的な存在です。はっぴいえんどでの活動後、自らの音楽的理想を追求するために「ナイアガラ・レーベル」を立ち上げ 、『A LONG VACATION』で大衆的な成功を収めました 。彼は、敬愛するフィル・スペクターのサウンドを日本に持ち込み、徹底的なスタジオワークで「音の職人」としての哲学を確立しました 。彼の音楽は、単なるメロディではなく、音そのものが持つ世界観を重視した、緻密な音響設計の上に成り立っています。
山下達郎:シティポップの「キング」として知られる山下達郎は、ビーチ・ボーイズをはじめとするアメリカン・ポップスから多大な影響を受けています 。彼は、自身のラジオ番組で長年にわたり「音質へのこだわりは半端ない」と公言するなど、そのサウンドに対する追求は徹底しています 。完璧なグルーヴと、聴く人の心に響くメロディは、彼の並外れた音楽的才能と、音楽制作に対する真摯な姿勢から生まれています 。
竹内まりや:夫である山下達郎との「ゴールデン・コンビ」が生み出した作品群は、シティポップの金字塔とされています 。特に彼女の楽曲「Plastic Love」は、YouTubeのアルゴリズムを通じて、時を超えて世界的なミームとなりました 。この楽曲が持つ普遍的なメロディと、都会的な恋愛をテーマにした歌詞は、リアルタイム世代だけでなく、新しい世代にも強く響いています。
 amane
amaneもしもこれからシティポップの世界に足を踏み入れる方がいらっしゃれば、私が強くお勧めしたいのは、山下達郎の『FOR YOU』です。このアルバムの冒頭を飾る「SPARKLE」のギターカッティングを初めて聴いたときの衝撃は、今でも忘れられません。夏の朝、海岸線をドライブする情景が目の前に鮮やかに広がり、一瞬で心が解放されるような感覚を覚えました。鈴木英人氏の描くジャケットアートワークと完璧に調和したこのアルバムは、まさにシティポップが持つ「音とビジュアルが一体となった世界観」を最も純粋に体現している作品だと信じています。
まとめ:シティポップが語りかける、もう一つの「今」
シティポップは、日本の経済的繁栄、都市化、そしてテクノロジーが奇跡的に融合して生まれた「文化的なタイムカプセル」でした。しかし、その物語は過去に留まりません。一度は衰退したかのように見えたこの音楽は、YouTubeやフューチャーファンクという新たな技術と文化の潮流に乗って、再び世界にその存在感を示しています。
これは、単なるレトロブームではなく、現代ならではの複雑な現象です。インターネットを介して、世代も国境も超えて共有される「憧れの美学」や「シミュレートされたノスタルジー」が、この音楽に新たな命を吹き込みました。シティポップは、過去の輝きを振り返るだけでなく、現代を生きる私たちが何を求めているのか、そして音楽が持つ本質的な力がどこにあるのかを静かに語りかけています。
さあ、あなたもこの都会のサウンドトラックを聴く旅に出てみませんか? きっとそこには、まだ見ぬ新しい発見と、心揺さぶられる感動が待っているはずです。


コメント