初回限定無料
CD派だった私が音楽サブスクに移行した理由~新しい音楽との出会い~

近年では、音楽の聴き方としてサブスクを利用する人が以前より増えましたよね。かつて著者は「音楽はCDで所有するもの」と固く信じる生粋のCD派でした。部屋を埋め尽くすCDの山、そして「音楽を聴きたい時に聴けない」不便さ。そんな悩みを抱えながらも、サブスクに抵抗し続けていた私が、あるきっかけでApple Musicと出会い、音楽との新しい関係を築くまでの心の変化を、正直な言葉でつづります。

saku
Webディレクター
日本最大手の音楽メディア編集者 | 5年間ディレクションやライターを担当。アーティストインタビューやライブレポート、特集記事の企画・編集を手がけ、数多くの音楽情報を届けてきた実績を持つ。
サイト最高11万PVを突破
音楽好きの知りたい情報を発信
複数サイトを運営するディレクター

はな
都内で働く20代後半の会社員。10代のころからロックバンドやアイドルのCDを多数所持していたが、現在は主にサブスクで音楽を聴いている。
・CDで音楽を楽しんできたけど、サブスクに興味がある人
・新しい音楽との出会いをもっと気軽に楽しみたい人
・自分の音楽の幅を広げたいけれど、何から始めればいいか迷っている人

音楽の聴き方は人それぞれですよね。レコードからテープ、CD、サブスクと移り変わる中で、時代の流れに合わせて変化してきた人も多いのではないでしょうか。この記事では、著者の体験を元にCDとサブスクの転換期についてもお伝えしていきます。
私の音楽遍歴と「CD命」だった過去
読者の皆様はじめまして、都内で会社員をしているはなです。突然ですが、皆さんは音楽をどうやって聴いていますか?スマートフォンでストリーミング?
かく言う私も、つい半年前までは生粋の「CD派」でした。音楽は「所有」するもの。この言葉が、私の音楽人生を象徴する合言葉だったと言っても過言ではありません。初めて自分のお小遣いで買ったCD(初めてはMr.childrenのSENSEでした。今となっては懐かしい思い出です。)
ジャケットのデザインに一目惚れして衝動買いした輸入盤。お気に入りのアーティストのCDは、初回限定盤はもちろん、タワレコ限定特典付きも全てコンプリート。部屋には壁一面にCDラックが並び、新譜が出るたびに嬉々としてお店に足を運び、あの独特のインクの匂いを嗅ぎながら歌詞カードを読み込むのが至福の時間でした。

CDは単なる「音源」ではありません。それは、アーティストが魂を込めて作り上げた作品そのものであり、その想いが凝縮された「物質」でした。ジャケットのアートワーク、ブックレットに書かれたメッセージ、隠しトラック…一つ一つに、手で触れられる喜びがありました。CDショップで新譜の棚を眺め、試聴機で初めて聴く曲に心を奪われる瞬間は、まるで宝探しのような高揚感があったんです。
「データなんて…」デジタル音楽への根強い抵抗感

「この曲が好き」という気持ちが募ると、迷わずCDを買い、自分のコレクションに加える。そうすることで、私はその音楽を「自分のもの」にできた気がしていました。まるで、大好きな作品の所有権を得たような感覚。だから、音楽ストリーミングサービス(通称:音楽サブスク)が台頭し始めた時も、「データなんて、音楽じゃない」と強く反発していました。形のないものは信用できないし、所有欲も満たされない。サブスクで聴くことは、音楽への愛情が足りない証拠だ、とすら思っていたんです。
周りの友人が次々と音楽サブスクに移行していく中で、「いつでもどこでも聴けるよ!」「めちゃくちゃ便利だよ!」と勧められても、私は首を縦に振りませんでした。
「でも、手元に残らないでしょ?」「音質もCDの方が良いんじゃない?」「好きな曲が急に聴けなくなったらどうするの?」
そんな言い訳を並べて、私はCDという「確かな形」にこだわり続けました。サブスクがどんなに便利だと宣伝されても、それはあくまで「レンタル」のような感覚。自分の手元にフィジカルな媒体がないと、心から音楽を聴いている気がしなかったんです。音楽は、手で触れ、目で見て、五感で感じ取るもの。それが私の音楽に対する気持ちの表れでした。
日本の音楽市場の変遷:CDからサブスクへの大きな流れ
私の個人的な経験は、日本の音楽市場全体で進行している大きな変化の一部を反映していると感じています。かつてCDが圧倒的な存在感を誇っていた日本の音楽市場は、近年急速にデジタル、特にストリーミングへと軸足を移しています。
 saku
sakuここでは、CDからサブスクの利用者が増えたことをデータで解説していきます。専門的な内容を含むので、著者に代わってお伝えしていきますね。
2023年の日本の音楽市場総額は3,372億円に達し、そのうち音楽ソフト(CD含む)が2,207億円(約65.45%)、音楽配信が1,165億円(約34.55%)を占めました。
このデータが示すのは、音楽ソフトが依然として市場の大きな割合を占めているものの、音楽配信の存在感が著しく増していることです。
特にストリーミングは音楽配信売上の9割超えとなる1,056億円を達成し、6年連続で2桁成長、10年連続でプラス成長を記録しています。一方で、ダウンロード配信は数量・金額ともに前年を下回る減少傾向にあります。
2025年には、音楽配信売上においてストリーミングが市場全体の9割を占めると予測されており、この傾向はさらに加速すると考えられています。
| 年 | 音楽ソフト合計売上(億円) | CDアルバム売上(億円) | CDシングル売上(億円) |
| 2023年 | 2,207 (対前年比109%) | 1,021 (対前年比105%) | 370 (対前年比114%) |
| 2024年 | 1,794 (オーディオ総売上、対前年比106.7%) | 1,169 (対前年比103.2%) | 624 (対前年比114.1%) |
この市場の動きは、ユーザーの音楽消費の価値観が「所有」から「アクセス」へと移行していることを強く示唆しています。ストリーミング売上が継続的に成長し、音楽配信の大部分を占める一方で、ダウンロードが減少している状況は、ユーザーが個々の楽曲を「購入して所有する」よりも、サービスを通じて広範な音楽に「アクセスする」ことを重視していることを示しています。
これは、ダウンロードに伴うデバイスへの保存やストレージ容量の制約から解放されたいというニーズの表れとも考えられます。ストリーミングは、これらの物理的・デジタル的な「所有」に伴う制約を取り払い、「いつでもどこでも聴ける自由」という新たな価値を提供していると言えるでしょう。
しかし、日本の音楽市場には独自の特性も存在します。世界的にデジタルが主流となる中で、日本ではCD販売が依然として音楽売上の大きな割合を占め、2024年でも微増を記録しています。特にアナログディスクは、数量で269万枚(前年比126%)、金額で63億円(前年比145%)と堅調な伸びを見せています。
これは、日本の音楽ファンが物理メディアに対して特別な価値を見出していることを示唆しています。アートワークや手触り、コレクションとしての価値、そしてアーティストへの「応援」の形としてCD購入が根強く、これは単なる市場の「遅れ」ではなく、文化的な背景やファン心理に根ざした「共存」の形態であると捉えることができます。
日本の音楽市場は、グローバルなデジタル化の波に乗りつつも、物理メディアが持つ「所有欲」「コレクター文化」「アーティスト支援」といった独自の価値が強く残り、デジタルと物理が補完し合う「ハイブリッド型」の音楽消費形態を形成していると分析されます。
音楽ストリーミングサービスの利用者数も着実に増加しており、2022年末には2,770万人であった利用者数は、2025年末には3,250万人への増加が予測されています。
有料サービス利用率は24.2%、無料サービス利用率は22.0%であり、2年前と比較して有料サービスで5.0%、無料サービスで8.7%利用率が向上しています。
また、音楽聴取方法として「定額制音楽配信サービス」の利用が昨年より4.5ポイントと大きく増加したことが報告されており、私が感じていた「時代に取り残されている」感覚が、客観的なデータによって裏付けられる状況が伺えます。
 はな
はなsakuさん詳しい解説ありがとうございます!音楽サブスクの利用率が変化する時代の流れが良く分かりました。
CD派が抱える「ひそかな悩み」:物理的な限界とライフスタイルの変化

私のような熱狂的なCD収集家が直面する問題は、個人的なものに留まらず、多くのCD愛好家が共通して抱える課題だと感じています。私が「ひそかな悩み」と表現したものは、物理的な制約と現代のライフスタイルの変化によって顕在化する問題点でした。
最大の悩みは、やはりCDの置き場所でした。私の部屋には、大小さまざまなCDラックが所狭しと並んでいます。最初は美しく並んでいたコレクションも、年々増え続け、いつしか収まりきらない状態に。床に積み上げられたCDの山は、見るたびに「どうにかしなきゃ」という重いタスクとして、私の心にのしかかってきました。
「もうラックを置くスペースはない…」
「かといって、CDを捨てるなんて絶対にできない…」
大好きな音楽のCDが、いつしか「モノ」としての重荷に変わっていく。この葛藤は、CDを愛する人ならきっと共感してくれるはずです。引っ越しを考えるたびに、この大量のCDをどう運ぶか、どう収納するかを想像するだけで、頭を抱えていました。まるで、愛するがゆえに抱え込んでしまった荷物のような存在になっていたんです。
CDの収納問題は、多くの記事で解決策が模索されている共通の課題です。直射日光や高温多湿を避けるといった保管方法 、ラックや棚、引き出し、収納ボックス、専用ファイルなど多様な収納方法が提案されています。しかし、これらの物理的な解決策は、根本的な「モノが増え続ける」という問題には対処できません。CDをデータ化したり、フリマアプリで手放すといった選択肢も提示されていますが、愛着のあるコレクションを手放すことには大きな心理的ハードルが伴います。
「聴きたい時に聴けない」不便さと高まるストレス
そして、物理的な問題に加えて、利便性の壁も感じ始めました。
【社会人になると音楽を聴く機会が減る理由】
・会社の仕事で疲れ切っている
・休日は家事で忙しい
・CDを取り込んで聞く時間がない
家でじっくり音楽を聴く時間は、会社員になってからはめっきり減ってしまいました。平日は通勤電車の中、デスクでの作業中、休日は家事をしながら…といった「ながら聴き」が主流に。
通勤中に聴くには、CDからPCに取り込んで、スマホに同期するという手間が必要です。これがもう、本当に面倒!新しいCDを買っても、すぐにPCに取り込む時間が取れず、結局積んだまま…ということが増えました 13。
「あの曲、今すぐ聴きたいのに、CDが家にあるから聴けない…」
「作業中に、気分転換に全く違うジャンルの曲を聴きたいけど、CDを入れ替えるのは面倒…」
こんな小さなストレスが、日に日に蓄積されていきました。音楽ストリーミングサービスのメリットとして「いつでもすぐに聴きたい楽曲が楽しめる」点が挙げられるように、私が感じていた不便さは、まさにサブスクが提供する価値と直結していると実感しました。
これらの物理的な制約は、音楽を聴く機会を減らし、結果的に音楽体験の総量を低下させていると言えます。現代のライフスタイルは、即時性や手軽さを求める傾向が強く、CDのような物理メディアは、その手軽さに欠けます。これにより、「聴きたい」という欲求が満たされず、ストレスにつながる状況が生まれていました。
これは、音楽が「所有物」から「日常に溶け込む体験」へと変化している現代の消費行動を反映していると言えるでしょう。CDの物理的な制約は、現代の多様な音楽聴取シーンにおいて、ユーザーの利便性を損ない、音楽との接点を減少させるという機会損失を引き起こしていました。
サブスクを使う友人とのギャップに感じる孤独

周りの友人たちは、ほとんどが音楽サブスクを利用しています。「最近、このバンドにハマってるんだ!」「これ、おすすめのプレイリストだよ!」と気軽に音楽をシェアし合える彼らを羨ましく思うようになりました。
私は話題についていけず、「その曲、CD出てないんだよね?」と的外れな質問をしてしまうことも。すると、友人は不思議そうな顔をして「え、サブスクで聴けるのに、なんでCDにこだわるの?」と。
この時、初めて「あ、私は少数派なんだ」と実感しました。この感覚は、データによっても裏付けられます。20代の有料聴取層は前年から7.8ポイント増加しており 、Z世代の音楽サブスク利用率も高いことが示されています 。私(20代後半)が友人との間で感じるギャップは、若年層の音楽消費行動の変化と完全に一致していると、後からデータを見て納得しました。
音楽はもっと気軽に、もっと自由に楽しむものだという、現代の常識から外れてしまっているのではないか。好きな音楽について語り合いたいのに、ツールが違うだけで会話が途切れてしまう。そんな寂しさと、少しの孤独を感じるようになっていました。
音楽消費行動の変化は、若年層の社会的つながりにも影響を及ぼしています。音楽の聴取方法が、単なる個人的な趣味を超えて、友人間のコミュニケーションツールや共通の話題形成に深く関わっているのです。
サブスクサービスは、プレイリストの共有やSNS連携(TikTok、Instagram、YouTubeショートなど)を通じて、音楽を「聴く」だけでなく「共有する」「共感する」体験へと昇華させています。CDに固執することは、この新しい形の音楽コミュニケーションから疎外されることを意味し、私が感じた「孤独」は、デジタルネイティブ世代の社会性における音楽の役割の変化を浮き彫りにしていると感じました。
音楽サブスクへの移行は、単なる利便性の向上だけでなく、現代の若年層における音楽を通じた社会的交流への参加を促すものであり、物理メディアに留まることは、その交流機会を失うことにつながる可能性を秘めていました。
決意のきっかけ:揺るがない「音楽への愛」が導いた新しい扉
CDに対する愛着と、日々の不便さとの間で揺れ動く日々。そんな私を音楽サブスクへと導いたのは、ごくごく些細なきっかけでした。しかし、それが私の音楽ライフにおける大きなターニングポイントとなったのです。
ある日、友人に「とりあえず無料期間だけでも使ってみたら?もしかしたら、はなの好きなアーティストの曲もあるかもよ?」と、半ば強引に(笑)とある音楽サブスクサービスの無料トライアルを勧められました。正直なところ、「どうせ自分には合わないだろうな」と思っていました。無料なら損はないし、すぐに解約すればいいや、という軽い気持ちで登録してみたんです。
アプリをダウンロードし、自分の好きなアーティスト名を検索。すると、私が持っているアルバムはもちろん、持っていないシングル曲や、ライブ音源までがずらりと並んでいることに驚きました。
「え、こんなにたくさんあるの…?」
その瞬間、私の頭の中にあった「サブスク=手元にない不確かなもの」という固定観念に、小さなヒビが入ったのを覚えています。
なぜApple Musicを選んだのか?
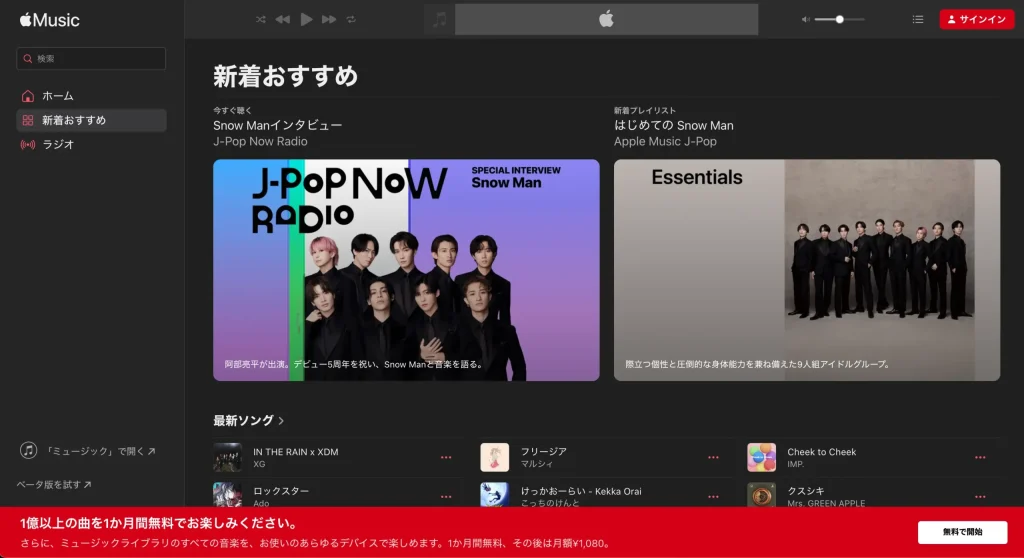
私がApple Musicを選んだ背景には、Z世代(私の年齢層に近い)からの高い支持があったことも大きな要因です。Z世代の音楽サブスク利用率ではApple Musicが34.3%で首位を占め、次いでSpotifyが25.2%となっています。この世代的トレンドは、私の選択が単なる個人的なものではなく、広範なユーザー層のニーズに合致していることを示しています。
Apple Musicは1億曲以上の楽曲を提供しており、これはSpotifyと同等の膨大なカタログです。さらに、Apple Musicはドルビーアトモスの空間オーディオやロスレスオーディオに対応しており、音質面で優位性を持っています。これは、CD派が重視する「音」へのこだわりにも応えうるサービスであることを示しています。
Apple Musicの料金プランは、個人プランが月額1,080円、ファミリープランが月額1,680円、学生プランが月額580円で提供されています。新規登録者には1ヶ月無料、対象デバイス購入者には3ヶ月無料のトライアル期間が設けられています。このような無料トライアルの存在が、私のように「どうせ合わないだろう」と思っていたユーザーの障壁を低くし、移行のきっかけとなったことは明らかです。
 saku
sakuApple Musicの料金プランや登録方法の詳細については、他の記事も合わせてチェックしてみてくださいね。
\初回登録は1ヵ月無料/
「CDでは出会えなかった音楽」との衝撃的なセレンディピティ
サブスクを使い始めて数日後、私にとって決定的な出来事が起こりました。
それは、何気なく聴いていたプレイリストからの出会いでした。普段、私が聴かないようなジャンルの「おすすめ」として、ある曲が流れ始めたのです。その曲は、とあるインディーズバンドのものでした。
(画像挿入)
「なにこれ…めちゃくちゃカッコいい!」
イントロから引き込まれ、聴き終わる頃にはすっかりそのバンドの虜になっていました。すぐにアーティスト名を検索し、他の曲も次々と聴いていきました。彼らの音楽は、CDショップではあまり見かけないし、私が普段チェックする音楽雑誌にも載っていなかったはず。もしCDにこだわり続けていたら、このバンドの存在すら知らずにいたかもしれません。
この「偶発的な出会い」は、私にとって大きな衝撃でした。CDショップの限られた棚や、自分の情報源だけでは、決して辿り着けなかったであろう音楽が、まるで魔法のように目の前に現れたのです。これこそが、音楽サブスクの真髄なのだと、この時、心から実感しました。
音楽の「所有」から「体験」へ、価値観のパラダイムシフト
この体験を通じて、私の音楽に対する価値観は大きく変わりました。
これまで私は、「音楽は所有するもの」だと固く信じてきました。CDという「モノ」を手にすることで、初めてその音楽を自分のものにできる、と。しかし、サブスクで新たな音楽と出会い、その無限の広がりを体験した時、ふと気づいたのです。
「本当に大切なのは、音楽を所有することではなく、音楽を体験することなのではないか?」
部屋に積み上げられたCDの山も、聴けない曲がある不便さも、もう私にとってのストレスではなくなりました。むしろ、サブスクを通じて、より多くの音楽に触れ、より深く音楽を楽しむことができるようになったのです。
もちろん、CDでしか得られない感動や所有する喜びがあることも理解しています。しかし、日常生活の中で音楽をより身近に、そして自由に楽しむためには、サブスクという選択肢がこれほどまでに強力だとは、想像もしていませんでした。
それはまるで、これまで「美味しい料理は自分で作って食べるもの」と思っていた私が、初めて世界中のレストランで手軽に美食を味わう喜びを知ったような感覚でした。私の音楽との関係性は、「所有」から「無限の体験」へと、見事にパラダイムシフトした瞬間でした。
Apple Musicの料金プランと無料体験の詳細
Apple Musicは、多様な料金プランと無料トライアルを提供しており、異なるユーザー層のニーズと経済状況に対応し、市場参入障壁を効果的に下げています。
 saku
sakuここでは、Apple Musicの料金プランについて詳しく解説していきます。音楽サブスクの選び方に悩んでいる方や、料金プランについて知りたい方は是非チェックしてみてくださいね。
| プラン名 | 月額料金(税込) | 年間料金(税込) | 主な特徴/メリット | 無料トライアル期間 | 無料トライアルの主な条件 |
| 個人プラン | 1,080円 | 10,800円 (2ヶ月分お得) | 1億曲以上聴き放題、広告なし、空間オーディオ、ロスレスオーディオ対応、オフライン再生、Apple Music Sing 19 | 1ヶ月 | 新規登録者のみ |
| 学生プラン | 580円 | – | 個人プランと同機能、Apple TV+無料特典付き 19 | 1ヶ月 | 大学・高専・専門学校在籍者、最長4年間 19 |
| ファミリープラン | 1,680円 | – | 最大6人まで利用可能(1人あたり約280円)、各個人ライブラリ 19 | 1ヶ月 | 新規登録者のみ |
| Apple Oneプラン | 1,200円から | – | Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, iCloud+をまとめて利用 20 | 1ヶ月 | 未登録サービスのみ対象 |
| 対象デバイス購入者特典 | – | – | 新しいApple製デバイス購入で適用 | 3ヶ月 | 新規登録者のみ、対象デバイス購入後90日以内 |
Apple Musicの多様なプラン提供は、単一の価格モデルでは取りこぼしてしまう潜在顧客層を取り込むための戦略であると考えられます。
学生プランは経済的な制約がある若年層の取り込みを、ファミリープランは複数人での利用による一人あたりのコスト削減を、Apple OneはAppleエコシステム全体での囲い込みを狙っています 。無料トライアルは、特に私のような「CD派」のユーザーが、金銭的なリスクなく新しい体験を試すことを可能にし、サービスの価値を実感させることで有料会員への転換を促します 。
無料トライアルの申し込みは非常に簡単です。iPhoneの「ミュージック」アプリを開き、「無料で始めよう」をタップし、希望のプランを選択してApple IDで認証するだけで完了します。無料期間中に解約すれば料金は一切発生しないため、安心して試すことができます。
 saku
saku私は個人プランとファミリープランがお得で使いやすく感じています。昔だったらTSUTAYAに音楽CDを借りに行ったのが良い思い出です。
 saku
saku今では、1000円弱支払うだけで1億曲以上の楽曲が聴き放題の時代ですからね…。あまり音楽を聴かない人ならYouTube MusicやSpotifyを使う方法もあります。Apple Musicは、音楽を日常的に聴く方にはおすすめのサービスです。
| おすすめの音楽サブスクリプションサービス3選 | |||
|---|---|---|---|
Apple Music | 【広告なしで1億曲以上が聴き放題】 ・Apple製品(MacやiPad)と相性が良い ・ダウンロードした曲をオフライン再生 ・ファミリープランで最大6人まで共有可能 | ||
Spotify | 【有料プランは機能制限なし】 ・無料プランと有料プランあり ・プレイリスト共有が無料で使用可能 ・音楽だけでなくポッドキャストも楽しめる | ||
YouTube Music | 【YouTubeをもとに音楽が聞ける】 ・音声のみモードで音楽を聴ける ・カバー曲やファンコンテンツが楽しめる ・無料プランでも特定の曲をフル再生できる | ||
\Apple Music広告なしで音楽が聴き放題/
音楽と新しい関係を築く喜びが待っている
私にとって、音楽サブスクへの移行は、音楽との関係性をより深く、より自由に、そしてより豊かなものに変えるきっかけとなりました。それは、CDへの愛情が薄れることではなく、むしろ音楽そのものを愛する気持ちを再確認し、その楽しみ方を無限に広げることでした。部屋はスッキリし、心にはゆとりが生まれ、何よりも「音楽ってこんなに楽しいんだ!」という純粋な感動が、私の毎日の生活を彩ってくれています。
もし、あなたが「CD派」というプライドと、新しい一歩を踏み出す勇気の間で揺れているなら、どうか安心して足を踏み出してみてください。そこには、あなたがまだ知らない、音楽との新しい喜びと発見が、きっと待っています。
 saku
sakuこの記事を読んでくださった方の音楽ライフが、さらに輝かしいものになることを心から願っています。
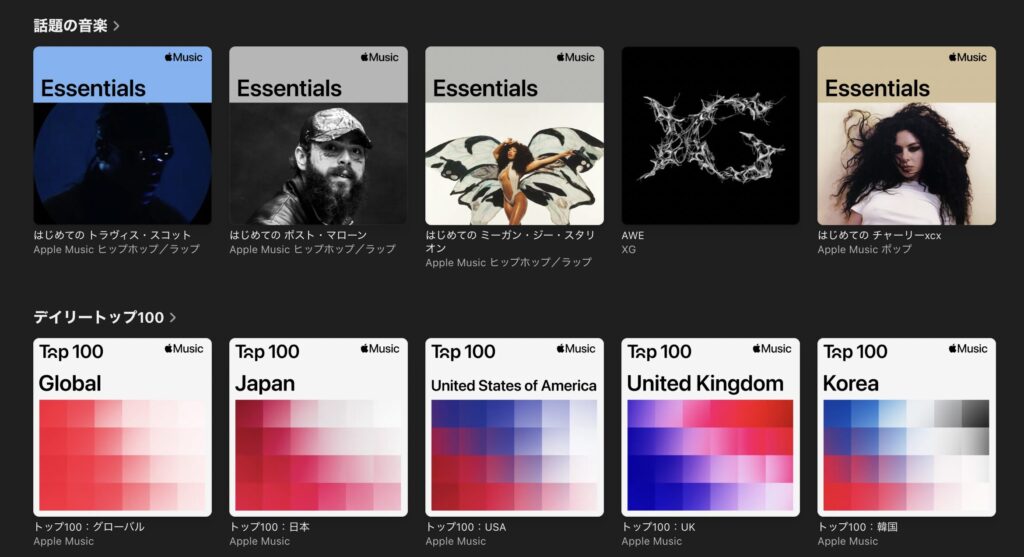
Apple Musicは、邦楽や洋楽など1億曲以上の楽曲が楽しめる音楽配信サービスです。
ダウンロードしておけばオフライン再生ができるので、通信量を気にせず音楽を楽しめます。
初回登録から1ヶ月はすべての機能を無料で体験でき、その後は月額1,080円で利用可能です。
\広告なしで音楽が聴き放題/
参考文献
日本のレコード産業 2024 – 日本レコード協会
https://www.riaj.or.jp/f/pdf/issue/industry/RIAJ2024.pdf
2025年第1四半期音楽配信売上は、前年同期比102%の317億円 – PR TIMES, https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000601.000010908.html
2024年 年間音楽ソフト売上動向発表 オーディオ総売上金額は前年比
https://www.billboard-japan.com/d_news/detail/146740/2
音楽媒体の変化 : CD からストリーミングサービスに移行する日本の音楽ファン https://www.arabnews.jp/article/features/article_26369/
サブスク音楽配信とCDはこれからどうなる? CDを持ち続ける方へ https://www.margherita.jp/user/column/subscription-music-distribution-and-cds/
【2025年】サブスク音楽配信サービスのおすすめ人気ランキング13
https://subsc.ooaks.co.jp/music
THE RECORD 2025年5・6月号 – 日本レコード協会
https://www.riaj.or.jp/riaj/open/open-record!file?fid=2039
2024年度音楽メディアユーザー実態調査報告書が発表 -若年層で音楽の無関心が増加傾向に
https://hotakasugi-jp.com/2025/04/01/music-news-2024-media-user-research/
大量のCD収納方法&保管方法をプロが解説!かさばらず傷まない探しやすい – ルミナスラック, 7月 3, 2025にアクセス、 https://perfect-floors.jp/blog/steel-rack/3502/
聴いていないCD・レコード。好きなものを持ち続けるための整理収納のコツ https://www.dinos.co.jp/furniture_s/article_storagetechnic/139/
CDやDVDが溢れている人への 片付けアドバイス, 7月 3, 2025にアクセス
https://tidearoom.com/cd_dvdseiri/
捨てられない。どんどん増えていくCDを保管するアイデア|risoco(リソコ) https://risoco.jp/proposal/housekeeping/1137/

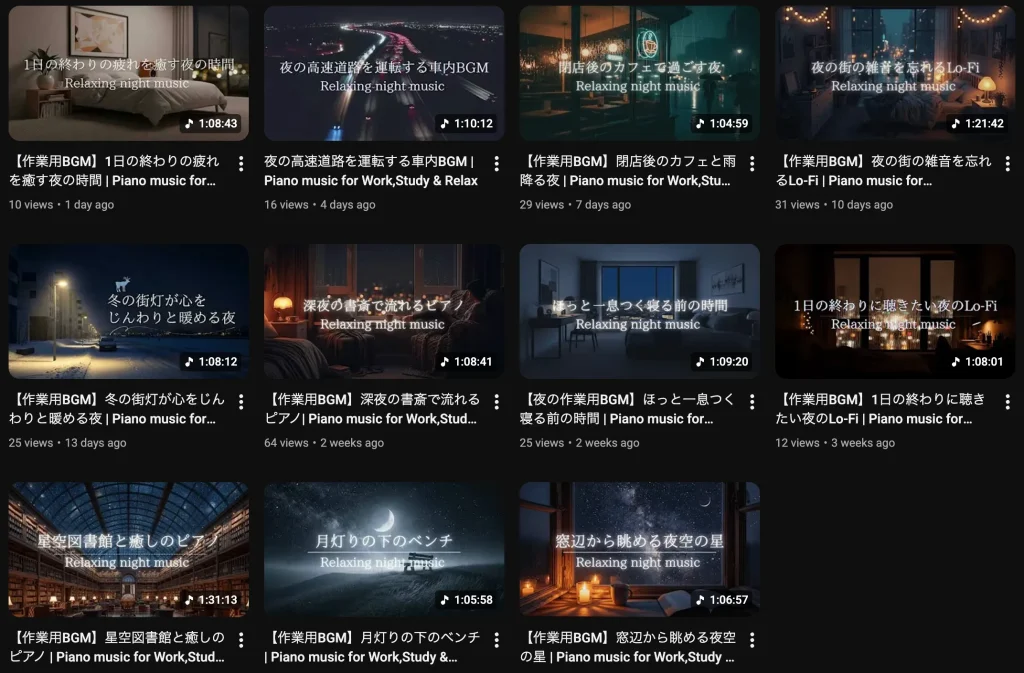



コメント